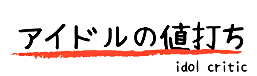秋元康は詩情を捨てることができるのか
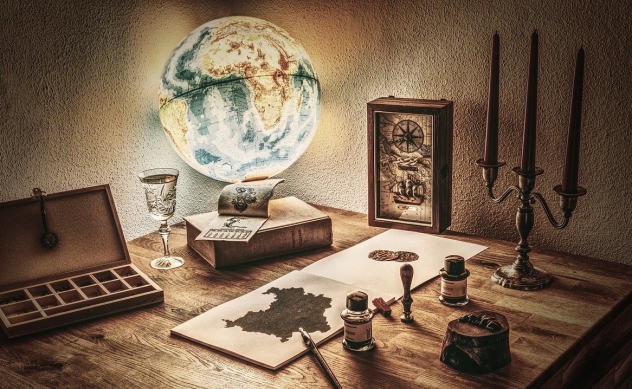
「櫻坂46の『BAN』を聴く」
いかに詩を扼殺するのか。
どのようにして、人は詩情を捨てることができるのか。
いやむしろ、このように問うべきかもしれない。ひとははたして詩を捨て、詩から脱却してしまうことができるのか。むしろ人間にとって詩とは、詩的なるもの、その感慨、叙情と呟きは、どうしようもなく我々につきまとってしまうものではないか。*1
櫻坂46の新曲『BAN』を聴いてまずおもったのは、秋元康は詩情を完全に捨てようとしているな、という点。もちろん、捨てようとしている、のであり、『BAN』の内に「詩情の扼殺」を目撃したわけではない。
作詞家を名乗る人間が詩情を捨てることができるのか、という問いは当然にしても、そもそも、秋元康はなぜ詩情を捨てようとしているのか、というところもとらえておく必要があるだろう。
欅坂46誕生以降、より正確に云えば『サイレントマジョリティー』以降、秋元康の「詩情の扼殺」の動機として、アイドルファンのあいだでもっと盛んに挙げられ指摘されているのが、尾崎豊への憧憬と模倣、である。そのポエトリーに対する倒錯の原動力を端的にあらわせば、おそらくそれは、作詞家の、物語を作ることへのこだわり、であり、つまり散文への過剰な憧憬と云えるだろう。さらにその散文へのあこがれが、生まれ持った作家としての性(さが)ではなく、作詞家として生きてきたなかで見出した希望であるとすれば、秋元康にその希望をあたえたものこそアイドルである、と読むのが妥当ではないか。秋元康が編み上げた音楽のなかで自己を語る、物語を作るのが現代でアイドルを演じる少女の宿命であるからだ。
自分がつくり上げた詩的世界に暮らす登場人物になりかわろうと試みるアイドルを目撃し、その少女の自己劇化を間近で眺めたのならば、当然、そのつづきが書きたくなる、はずだ。そのつづきが見たくなる、はずだ。詩ではなく物語を作ろうという意識の働きかけが強くなり、それに衝き動かされてしまう、のではないか。物語を書こうとすれば、文章や描写が長くなってしまう。よって詩情から遠ざかることになる。詩情をかなぐり捨てようと試みているように映る、ということである。もちろん、散文でなければ物語は作れないのか、という反問もあるにはあるが、それは論じるまでもなく各人の資質に還元される話題と云えるだろう。作詞家・秋元康の場合、意識的に物語を作り語ろうとすると、詩が、文章が、言葉が冗長になったり、たとえば啓蒙が抑えきれなくなり、詩情が野ざらしに遭う、ということにすぎない。
秋元康が詩情を捨ててしまう動機に、アイドルの物語化、がある、と仮定したうえで、作詞家は、はたして本当に、真に詩情を捨てきれるのか、問う。
なぜ人が時に詩への別れを唱えるのか。
それは、詩が甘やかで柔らかな、タフタのヴェールを現実にかけてしまい、しっかりとくるいなく認識をすることを、容赦なく感触を掴みきることを、不可能にするからだ。
だが、にもかかわらずもっとも決然とした認識の試みに際して、詩は執拗なその姿をあらわしてしまう。それはどうしても私たちが、人間が、ぎりぎりの現実と直面できないという宿命を、弱さを示すものにほかならないのだろうか。*2
アイドルファンとは身勝手なもので、音楽・歌詞のなかにアイドルの素顔=魅力を「しっかりとくるいなく」記せ、と強く希求するにもかかわらず、アイドルを物語ることの最も有効な手段であろう散文詩を、毛嫌いする。だらだらとだらしない言葉を書き連ねる作詞家を痛烈に批判する。
この、言わばアンビバレントの上を歩く作詞家・秋元康が「ぎりぎりの現実と直面できないという宿命」の側に倒れ込む光景、それがもっとも簡明にあらわれたのがNGT48の『絶望の後で』であり、アイドルを演じる少女たちに直撃した絶望を前に、しかしその現実との直面を回避し、なおかつ、作詞家としての立場をより堅牢に仕上げた工具こそ、ほかでもない「詩情」である。
プロデューサーとして働く秋元康の言説や立ち回りなかに脇の甘さを見ないのは、プロデューサーであると同時に作詞家として振る舞い、詩情を駆使することで現実との直面を回避し、詩情を活用することでフィクションという体裁のもとに現実を撃てるからである。プロデューサーとして、あるいは作詞家として、差し出した、「山口真帆暴行被害事件」への回答も、それが詩という形式に則ったものである以上、どのような解釈も許可するということであり、裏を返せば、どのようにでも言い逃れることができる、という意味をもつ。
つまり詩作とは、現実を俯瞰し、現実の再構築を試みるといった、いわば超越的立場につくことであり、創造にほかならない。作詞家が創造した世界である以上、現実を無視しあらゆる絶望を愛へと変換する物語が眼前に広がっても、もはやだれも隙を突けないのである。そして、この超越的な立場、世界を創造する存在、という意識が、いよいよ、『BAN』においてつよくあらわれたわけである。
神様 過ちを許して下さい 急にそんな宣告をするなんて*3
『BAN』における”神様”を、それを記した作詞家本人とするならば、オンラインゲームをプレイするユーザー、つまり現実とは異なる場所でもうひとりの自分を育て、やがて”神様”にBANされてしまう主人公は必然的にアイドルを演じる少女自身となる。オンラインゲームという仮想空間においては、アイドルシーンといったきらびやかな非日常を映す架空の世界においては、本来、信じる信じないといった話題に立つ”神様”という超越的存在が、しかし信じる信じないといった問いかけをするまでもなく、絶対的に、確実に存在する。その”神様”の働きかけによって、これまで大事に育ててきたもうひとりの自分を、ある日唐突に、一方的に失う、という物語が『BAN』である。ようするにこれはこれまでにも作詞家・秋元康がくりかえし描いてきたアイデンティティの喪失の物語であり、近年ならば、乃木坂46の『僕のこと、知ってる?』とおなじ棚に分類されるだろう。
『BAN』独自のおもしろさを探るとすれば、自我の喪失イベントがほかでもないプロデューサーから下される点にあるだろうか。『BAN』で描かれるBANがアイドル界からの追放であるならば、当然それは現在のシーンがかかえる病弊への、”アイドル”でありつづけなければ夢は叶わないと盲信する人間への痛烈な皮肉ととらえることが可能である。楽園から追放された、あるいは追放を予感した、いつのまにか大人になっていた少女は、いまさら違う自分にはなれるわけない、と怯える……。ついには、追放されてなるものか、とひらき直る。ちなみに、オンラインゲームにおいてそのしきたりをやぶり、BANの宣告を受け、楽園から追放された人間に共通するのは、この追放は誤りだ、なにかの間違いだ、という一貫した主張であるらしい。そのような醜態を、未練がましさをアイドルシーンにかさねてみれば、『BAN』がよりアイロニカルな作品に見えてくるのではないか。
作詞家・秋元康は詩情を捨てることが可能か、冒頭の問いかけに戻れば、『BAN』において、詩作にあたり超越的な存在として屹立し、さらには歌詞の内に自身をそのまま超越的存在=神様として直接配置した大胆さ、厚顔さには、たしかに、詩情の扼殺、その兆しを見ることができるかもしれない。
とはいえ、その構築された詩的世界がアイドルシーンにたいする遠回しな啓蒙、あるいは、現実との直面を避けた皮肉、あてこすりに満たされる以上、やはりそれは詩情と呼ぶほかないだろう。
2021/03/13 楠木かなえ
引用:*1~2 福田和也/ダ・ヴィンチ「金子光晴」
*3秋元康/BAN