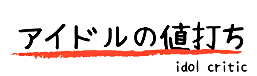まえがき
アイドルってなんだろう?
ほんとうの自分、ほんとうの夢を探すため、自分とは別の何者かになりきり、日常を演じ、やがて偶像になる……、この少女たちを取り巻く現在のメディア、コラムニスト、ライターが書き立てる言葉はあまりにも月並みで、無内容であり、言葉のちからを持たず、私の疑問にはまったくこたえてくれない。
「作家の値うち」を読みながら、ふと、小説を批評するのとおなじようにアイドルに点数を付けたらおもしろいのではないか、遊び心を宿した。この「おもしろさ」を前にして、きっと多くの人間がある種の不純さと同時に滑稽さを感じ取るのではないか。けれど、アイドルを真面目に語ることにどこか滑稽さを感じてしまうという点にこそ今日のアイドルシーンのイロがある、と云えるのではないか。アイドルを眺める人間が、アイドルを真剣にとらえることができないからこそ、アイドルを演じる少女たちは無垢な称賛や中傷にさらされるのだ、と。
アイドルを真剣に語る、真剣に考える手段として私は「批評」つまり「文学」を準備する。
文学とは人間のありのままのすがたをうつし出す作業だ、と云ったのは誰だったか。夏目漱石はニートを、大江健三郎は宗教とテロルの緊密を、村上春樹は現代日本人が抱える空虚と無関心を、それらを象徴とする時代がおとずれるよりも前に、小説を書き、”来るべきものの側”として撃った。しかしそれは予言などではなく、人間の機微を、日常を写実し物語った結果にすぎない。日常がフィクションの内に描かれたのならば、当然、そこには私たちの未来が立ち現れる。優れた文学小説に描かれる登場人物たちの「生活」は、私たちの「生活」でもあるのだ。もちろん、アイドルもそこに含まれる。文学テクストとして生動する架空の登場人物たちの横顔に、少女たちが編み上げる幻想=アイドルを重ねる行為は、その偶像への接近を許すのではないか。
KRUSHを聴きながら、「魔の山」を読み、ときに小説を、ときには演劇を批評する、物書きの端くれ。虚構の扉をひらき、アナザーストーリーを描く少女たちに自己を投影し、「ヴァンヌイユ」を名乗り膨大な数の批評を編んだルバテみたいに”僕”も、もうひとりの自分を、もうひとりの作家「楠木かなえ」を名乗り、架空の世界の住人を演じてみる。「福田和也」をバイブルに、小説を書くように批評を作った「小林秀雄」を勇気と活力に、ブレイクビーツのように文豪たちの言葉を引きながら、儚さの内に活力をふりまくアイドルの素顔を、自我を探し求め迷子になる少女たちの物語を追いかけてみる。ユリウス・カエサルに”恋”をした塩野七生のように、ヴァリエテ座で踊るナナを”金蝿”と批評したフォシュリーのように、アイドル史をひとつの長編小説として眺め、架空の世界に生きる少女たちの日常を手繰り寄せ、物語ってみよう。
――そこに書いてあるのは、私のことだっていうんだけど、とナナは、興味なさそうな振りをしながら言った。
…『金蠅』という題のフォシュリーの記事は、或る淫売婦の物語で、四五代大酒飲みの続いた家系に生まれて、多年に亘る貧困と飲酒の遺伝のために血が汚され、それが彼女にあっては、性の神経的な変調という形で現われているというのだった。この娘はパリの場末の舗道の上で成長し、充分な肥料を施した植物のように、丈高く、美貌で、素晴らしい肉体を持って居り、自分の祖先である乞食や浮浪者たちのために復讐の日夜を送っている。彼女を通じて、庶民の間に醸成された腐敗堕落の風は、貴族階級に及んで、これを腐敗させつつある。彼女自身にその意志はなくとも、その雪を欺く腿の間で全パリを腐敗解体させ、恰も女が月々牛乳を変敗させるように、全パリを変敗させる破壊の酵母、自然の力の如きものとなっている。…この女は、汚物から飛び立った一匹の金色の蠅である。路傍に放置された腐肉から死を取り来って、羽音も高く踊り狂い、宝石のように煌めきながら、宮殿の窓に飛びこみ、人々の上にちょっと留まるだけで彼等を荼毒する金蠅である。
ゾラ/ナナ(訳 川口篤・古賀照一)
2018.07.10 楠木かなえ