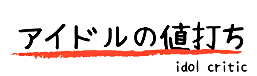乃木坂46 川村真洋 評判記

「アーティスティック・アイドル」
川村真洋、平成7年生、乃木坂46の第一期生。
歌が飛びきりに上手い。ダンスも目をみはるものがある。アイドルらしからぬその実力をもって、「アイドル」のことを嘲笑い遠ざける一般大衆に真正面から立ち向かうように、アーティスティックに自己を表現しつづけた点は評価されてしかるべきだろう。乃木坂46の歴史にあっても、乃木坂らしさ、という文言に一切縛られず、ポップカルチャーそのものに呼応しようと試みるなど、曲がらない何物かを有した心強い登場人物である。
それゆえか、ファンからの評価よりも、作り手、同業者からの評価のほうが格段に高い。アンダーの身でありながら、多くの作品で歌にダンスにと、選抜メンバーを牽引し、支えつづけた、という意味では「評価」ではなく「信頼」と表現すべきかもしれないが。西野七瀬、齋藤飛鳥を継ぐ若手アイドルが一向に現れないのと同じように、この川村真洋の面影をもった少女が出現しないこともまた、川村が希有であることを教えている。
総合評価 60点
アイドルとして活力を与える人物
(評価内訳)
ビジュアル 9点 ライブ表現 16点
演劇表現 9点 バラエティ 13点
情動感染 13点
乃木坂46 活動期間 2011年~2018年