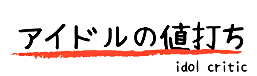欅坂46 平手友梨奈 評判記

「時代の寵児」
平手友梨奈、平成13年生、欅坂46のオープニングメンバーであり、初代センター。
平成のアイドルシーンにおいて最も嘱望されたアイドルである。『サイレントマジョリティー』発表後、常に話題の中心に置かれてきた。『二人セゾン』『アンビバレント』などの傑作はもとより、欅坂46名義でリリースされた8枚のシングルすべてでセンターポジションを担った。これはAKB48から連なるグループアイドルの歴史において前人未到の快挙である。真に突出した境遇の持ち主、時代の寵児と呼ぶべきだろう。
『サイレントマジョリティー』をもって、大人への反抗、というジャンル、枠組みをシーンに決定づけたその鮮烈さ、衝撃、平成のアイドルシーンを代表する傑作を生んだことの余韻の強さをして、目まぐるしいスピードで成長・変化を遂げていく自己の姿を目の当たりにしながら、しかし一方では、大衆と対峙し、常に、大人への反抗、を歌わなければならないことの、破滅への予感、言うならば、何者にもなり得ない、という、アイドルを通し日々育まれたであろうその屈託した佇まいにはカリスマと呼ぶに値する冠絶した孤独感が宿っている。
自我を獲得する前に自我を喪失してしまった、パラドクスに揺れる、蹌蹌踉踉(そうそうろうろう)としたその踊りの表層に導かれた笑顔は、これまでのアイドルには表現し得ないものだった。その横顔は、たとえば、アイドルを眺める者に、夢を諦めたことを後悔させるような、魔力を宿している。ゆえにこの人は、ある種の幼稚さを支えにして隆盛を誇るアイドルシーンにあって、唯一、その枠から抜け出ている。
総合評価 87点
現代のアイドルを象徴する人物
(評価内訳)
ビジュアル 16点 ライブ表現 20点
演劇表現 17点 バラエティ 16点
情動感染 18点
欅坂46 活動期間 2015年~2020年