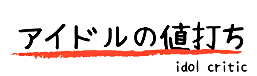AKB48 秋元才加 評判記

「アイドルらしくないアイドル」
秋元才加、昭和63年生、AKB48の第二期生。
演技、とりわけ舞台・演劇における巧者とされる。
役者・俳優という職業に向ける鼻息の荒さ、力の入れ方には並ではないものがある。増田有華と並び、「グループアイドルと演劇」という話題において先陣を切り、同業者から惜しみない賞賛をうけている。
たしかに、日常から遠く離れた感情に蟠踞する彼女の演技は、ずば抜けたものだろう。一方で、現実感覚に薄れたその演技は、アイドルのたかぶった生の感情をファンに伝えることを拒んだようでもある。
アイドルらしくないアイドルだと、自己皮肉も含め、喧伝されたが、それは正しくもあり誤りでもある。ルックスに関してならば、大衆のイメージするアイドルらしさ、要するに可憐さや愛嬌を著しく欠いたメンバーであることは否定できない。けれどアイドルとしての有り様、たとえば自身の関心を追究していくそのスタイルにかもし出される秋元のビジュアルは、まさしくAKBの魅力そのものであり、つまり今日のアイドル観に一致している。卒業後、大衆を向こうに回し披露した、ジェンダーにたいする個人的な葛藤、屈託も、その一環に過ぎない。
問題は、いや、幸か不幸か、と云うべきか、秋元が現役アイドルだった当時とは大きく異なり、現在のシーンには「秋元才加」を軽く凌ぐ演劇の才をもった少女がきら星のごとく存在する、という点だろうか。
総合評価 59点
問題なくアイドルと呼べる人物
(評価内訳)
ビジュアル 13点 ライブ表現 13点
演劇表現 14点 バラエティ 12点
情動感染 7点
AKB48 活動期間 2006年~2013年