現役の作家から見たChatGPT(AI)の魅力と影響力
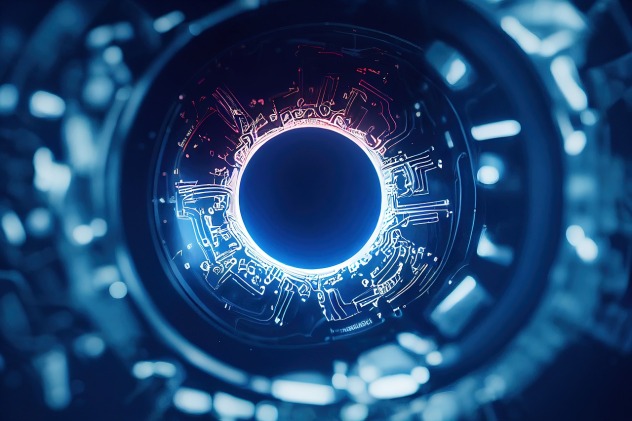
「AI以前の作家と、AI以後の作家の誕生」
日本人ってえのはな、静かで控えめで小さなものの中にだけ、価値を見つけるんだ
矢作俊彦/あ・じゃ・ぱん
最近は、戦後日本の偽史を描いた矢作俊彦の小説『あ・じゃ・ぱん』に着想を得て、ほとんど遊び心から乃木坂46の佐々木琴子の偽史批評をこつこつと書いている。『バレッタ』において鈴木絢音とのダブルセンターでデビューを飾った佐々木琴子への批評なのだが、書きながら、ふと、これはあるいは今世間を騒がせている「ChatGPT」による文章だと読者に勘違いされてしまうのではないか、『アイドルの値打ち』を学習したAIがそれっぽく書いた文章だと捉えられてしまうのではないか、と考え、困惑した。なんともまあ傍迷惑な……。
と、まあそうした個人的な事情はともかく、「ChatGPT」への報道、またその報道に対する世間の反応を眺めながら私が注目したのは、世間の人たちは思いのほかAIのことを「脅威」として捉えているのだな、という点。AIの目ざましい成長によって人間の多くの仕事が奪われると震え上がる人、とか、AIを全知全能の神のように崇める人、とか、そうした人たちの恐怖・不安、また信奉はおそらくSF小説・映画などのフィクションを原動力にしたものだと想像するが、現実に目を向ければ、AIは私たち人間の人生をより豊かにするツールであり、脅威などどこにもない(もちろん、社会の様相がものすごいスピードで変わっていくことの不安はあるかもしれない。また、SF的恐怖にならえば、AIに自分の名を訪ねたら伝記作家のようにその人生を叙述される、といった、いわゆる個人情報に関する不安もあるにはある、ようだ。たしかに、何月何日にどこどこの店で何々を買った、とか言い当てられたら、すこし、いや、かなり不気味ではある)。
たとえば、物書きの視点、小説の批評、演劇の批評を書くことで生活を成り立たせている私の視点から物を言わせてもらえば、AIが私の生活の中心である「文章を書く」という行為を奪うことはまず起こり得ない、と断言できる。なぜなら私たち物書きは書くことで考え成長することに目的があるのだから、これから先、AIが人間とまったくおなじ水準の文章を書けるようになったとしても、それが直接作家の行動力に関わることはないし、作家としての営為に打撃を与えることもない。書きながら、自分がどういう答えにたどり着くのか、というところに文筆のおもしろさがあるので、AIが登場したからといってその時間が奪われることは考えるまでもなく、あり得ない(当たり障りない、誰にでも書ける文章を書くコラムニスト、Webライターなどは「作家」とは呼べないから、この話題には当然、含まれない)。
むしろAIは、孤独の夜半に文章を書き、朝、覚めてそれを読んでは書き直し、という終わりの見えない日常の反復に生きる作家の頼もしい相棒=忌憚のない意見をくれる読者、ときには文章を厳しくチェックしてくれる編集者になってくれるのではないか。作家とは、なんといっても編集者との出会いによってその命運を分ける職業なのだ。AIに編集者が務まるのか、という話題に関しては、作家の立場にある私には言及することができないから、ここでは触れないでおく。
とはいえ、AIが頼もしい相棒になるには越えなくてはならない壁があるようだ。
「ChatGPT」を試してみると、堀辰雄の代表作がなぜか『ドグラ・マグラ』だったり、チャップリンの『独裁者』の登場人物のなかにハイドリヒの名があったり、まだまだ粗い。正直、使い物にならない。現状は、100回質問したとしても、欲しい答えが返ってくることは1回もないだろう。けれど、そうした情報の正確性への不安の解消はもはや時間の問題であり、さして重要ではない(インターネットから情報を拾い集める仕組みが変わらない以上永遠に解決されないようにも感じるが、その仕組みが根本的に変われば、すんなり解決するようにも思う)。
問題は、現在のAIは「発想」を備えない点で、現在のAIに触れるに、どうやらアイデアという概念をもたないらしい。これはおそらく研究者のなかでこれまでとは桁違いの大きなブレークスルーを必要とする話題なのだろうと想像する。人間は言語でできている生きものだから、人間を再現するには言語のマスターが必要になる。言い換えれば言語さえマスターしてしまえば人間は再現できる、ということなのだが、言語をマスターするには当然「発想」を備えていなければならない。よって、AIが人間とおなじように文章が書ける、という地点がAIの進化における最終到達点であると私は考える。
人間とおなじような文章を書くことと、人間とおなじように文章を書くことでは、大きな隔たりがある。
たとえば、ある小説の比喩表現を前にしたとき、AIはそれが「比喩表現」として書かれたものであることは判別を可能にするだろうけれど、それが何を意味しているのか、自分で考えることはできない。あくまでも過去の作品のなかで書かれた「比喩表現」を解説している人間の言葉から答えを探すことしかできない。
文芸批評でたとえれば、小説家がとくに深い意味もなく書いた一つの言葉に注目し、それをまったく別の事柄に結びつけ、新しい価値を作り出す、という行為は現在のAIには理解できないものであり、AIは作家が意味もなく書いた言葉は、そのまま意味のない言葉だと、一つの判断・選択しか持つことができない。人間とおなじような文章を書けるようになることはAIの進歩の初歩だが、人間とおなじように文章を書けるようになることはやはりAIの進化の最終到達点なのだ。
もちろんAIに秘められた可能性に疑いの余地はなく、東京大学が「ChatGPT」の登場をカエサルがルビコン川を渡った日の衝撃にたとえていたが、まったくそのとおりだとおもう。今年AIは、人類は、ある意味でルビコン川をまた越えた。これは馬から「くるま」に変わったとき以上の衝撃だと想像する。
おもしろいのは、このAIと人間の新世界のスタートが人類に平等に与えられているという点だろう。車が誕生した時、それはまだまだ多くの人間にとって特別な出来事、存在であり、カウボーイは馬に跨っていた。しかしAIは違う。AIは誰にでもすぐ使える。この点が興味深い。
誰でもAIを使える、ということは、誰かがAIでやれることは誰にでもできる、ということだ。たとえばドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の続編をAIに書かせ、それが読み応えのある魅力にあふれた作品になっていたとしても、それが誰にでもできることならば、当然、それに価値を見出すこともまた誰にもできない。
AIが一部の人間だけに許された技術品であれば話はまったく変わったはずだが、不思議なもので、そうはならなかった。人は特別なもの、入手するのに苦労するもの、つくりあげることに並ならぬ才能と労力がかけられたものに、憧れる。苦労なく誰にでも平等に与えられるものには、価値を見出だせない。
一瞬で出来上がるAIの小説を時間をかけて読む人間がどれだけいるのか。最初は目新しさもあって、一定の読者を得るかもしれないけれど、すぐに飽きてしまうのではないか。もしかするとこれはもう、心のなかですでにAIを差別しているのかもしれない。所詮はAIが作った小説だろ、と。AIに求めるのは情報の提供であって、芸術ではない、と。誰にでもできることは、きっと、芸術にはなり得ない。
つまりこれからは、なにをやったのか、ではなく、どこの誰がやったのか、という点が重視されるのだろうし、すでに著名の士に数えられている人物、世に名が出ている人物、名が売れている人物、なにかを成し遂げた人物はそのまま過去の情報として高い価値をはらむだろうから、AIと人間の世界において有利な立場を築くはず。
作家でいえば、この2023年までにそれなりの賞を受賞してしっかりと文壇デビューしている人物はこれから長い時間、高い優位性を示すのではないだろうか。一方で、これからデビューする作家は現在の出版不況とはまた別の視点から、厳しい立場に置かれる。AIという存在を読者はもう無視することができないはずだから、なにを書いても「これはAIが手伝っているんじゃないか」という視点を自身の作品に向けられてしまうだろうし、なによりも、前述したとおり、作家自身、AIと歩調を共にした作品づくりに励むことになるはずだ。よって、カエサルのルビコン渡河によって運命を決したローマ史のように、2023年までの作家をAI以前の作家と呼び、これからの作家はAI以後の作家として、分類されるのではないか。
AI以後の作家、小説に見出されるテーマ、見どころは、もはや自分が書く必要はどこにもない、と夢を挫折する作家志望の若者たちのなかにあってなお「書く理由」をもつことの、その意思の発露、になるのではないか。
2023/04/06 楠木かなえ
