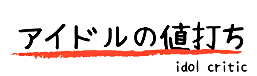引用と密接になってしまう、アイドル

「私に固有でないものが寄り集まって私になる」
無意識は「他者の語らい」として規定される。事実、自己が語ることがらは、物語化されており、したがってナルシシズムに侵されてしまっているから、信用できるのは他者からくる言葉だけである。ところが、他者から来る言葉だけを吐いている人間は、どう見られるだろうか?自己責任の取れない人、ということになる。どちらにしても自分らしさというものは期待できない。だから、人格というものがあるとすれば、それは、他者から来た言葉とナルシシズムとの組み合わせ具合として定義されることになる。人格とは、その組み合わせ具合の、その人ごとに最も安定したあり方、ということになる。
新宮一成/精神分析の21世紀
人は、アイドルは、なぜ引用をやめられないのか。大仰に言えば、なぜ引用のとりこになってしまうのか。新宮一成の言葉はこの問いかけへの答えを、ひとつの側面から与えてくれる。
『精神分析の21世紀』を『小説の自由』において引用した保坂和志は右のように述べている。「もともと人間の脳は、柔らかいテープレコーダーといった趣の物体であって、他者の語らいを忠実に記録している」、「人間は、成長して、それを自分の言葉であると思い込んで外に出すように出来ている」、と新宮一成の文章をあくまでも自分の「言葉」として、述べている。この「成長」をそのまま物語にして語った作品こそ、ほかでもない保坂和志の傑作小説『季節の記憶』なのだが、同作においては、人は言語でできた生き物であることを、登場人物たちが繰り返し語り合っている。保坂和志/新宮一成の言葉・文章を鵜呑みにし要約すれば、次のようになる。人は言語の先立った、言語で成り立った生き物であり、またその「言語」は、他者の言葉の集積、言うならば過去の堆積である。つまりこの事実は、私たちが引用から逃れることができない運命にあることを教えている。*1
引用が、その人の人格を決定づけることは、もはや明白だ。引用、つまり、他者の言葉を借り自己を表現するという行為にかもし出されるある種のブッキッシュな佇まい、ペダントリーは、ここでは問題にならない。考えるべきは、引用が引用者の人格を決定づけるという、一点でしかない。
枠にはまった平凡な人にとっては、自分こそ非凡な独創的な人間であると考えて、なんらためらうことなくその境遇を楽しむことほど容易なことはないのである。ロシアの令嬢たちのある者は髪を短く切って、青い眼鏡をかけ、ニヒリストであると名乗りをあげさえすれば、自分はもう眼鏡をかけたのだから、自分自身の《信念》を得たのだとたちまち信じこんでしまうのである。…またある者は、何らかの思想をそのまま鵜のみにするか、それとも手当たりしだいに本の一ページをちょっとのぞいてみさえすれば、もうたちまちこれは《自分自身の思想》であり、これは自分の頭の中から生まれたものだと、わけもなく信じこんでしまうのである。
ドストエフスキー/白痴(木村浩 訳)
こうやって引用への皮肉を物語のなかに象ることは如何にも小説家らしい振る舞いなのだが、ドストエフスキーのこの皮肉はアイドルを演じる少女をもまた囚えてしまうのではないか。アイドルとは、いや、アイドルを演じる少女にとっての「アイドル」とは、自分ではない別のもうひとりの自分、であるはずだ。たたでさえ、他者の語らいを蒐集することは生きる上で欠かせない営みであるのに、そこにもうひとり、別の自分を作り上げるとなれば、なおさら引用の力に頼ることになる、はずだ。
ファンの期待にこたえる、自分の理想を叶える「アイドル」を作り出すために、少女たちは他者の言葉、過去のテクストを蒐集し、その人格を決定していくのではないか。その結果、清楚・処女であることを誇示するアイドルだったり、髪を金色に染めたアイドルだったりが、誕生するのではないか。
「引用」には、「それによってある権威が付与されるような効能がある」。それは、「引用箇所は真偽を問われない(問われにくい)」あるいは「なかば自動的に引用箇所が真理として機能する」という点である。「引用箇所は数学の定理と同等の価値を持つ、証明済みの信じるに足る事項であるという錯覚を読者に与えやすい」。ならば当然、引用を多用するアイドルはファンに一目置かれるような存在になるだろうし、また同時に、その「錯覚」に目ざといファンは、”彼女”のことを訝しむことだろう。*2
こうした「引用」において、引用者が読者に不快感を与えてしまう場面があるとすれば、そのほとんどは、文章の主従関係が逆転していることに端を発する。他者の語らいを蒐集し人格を決定していくなかで、書物やインターネットの世界から拾い上げたばかりの言葉を世間に向け披露したいという欲に負けて、知識を披露することだけを目的にした文章を編み上げ「引用」を破綻させてしまう書き手は、ごまんといる。自分が何を言いたいのか、書きたいのか、伝えたいのか、明瞭なテーマを握りしめてさえいれば、その文章を物語るために、あるいは権威性なるものを付与するために「引用」を継ぎ足し、言葉を編むようにして文章を再構築すればいいだけの話なのだが、知識をひけらかしたい、という誘惑に、往々にして、人は負けてしまうようだ。あるいはその種の人たちのことを、凡庸、と呼ぶことができるかもしれない。
裏を返せば、それだけ「引用」には並ならぬ希求があるということなのだが。
いずれにせよ、人が自分らしさを獲得するために「引用」が欠かせないことは、まず間違いない。引用を経ずにアイデンティティを確立するなど、誰にもできない、と断言しても良い。と、ここまでに書いたすべてが、ただの励ましにすぎないのだけれど、引用の未熟さも、情熱に導かれた先走りに過ぎない。
負けるな、しょげるな、林瑠奈!
二十世紀以降の、前衛的な小説家たちが試みた実験は、はたして継承可能だろうか。それは、実験であり、野心的な試みであったためにまた、唯一度しか試みられえないものではなかったか。
前衛的な試みが継承不可能であるのは、何よりもそれらの実験が、小説の、テクストの破壊破裂を目的としていたがためにほかならない。
もっとも唯一、継承され、発展したと呼べる手法がないではない。
引用である。
そして、引用が、今日さまざまな領域でいよいよ隆盛を誇っているのは、何よりも引用が、すぐれて統一性と同質性を徹底的に破壊するための技術であるからだ。
福田和也/現代文学
2021/02/28 楠木かなえ
引用:見出し、*1~2 保坂和志/小説の自由