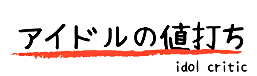乃木坂46を、群像劇と呼べる理由

「アイドルの可能性を考える 第五十三回」
メンバー
楠木:文芸批評家。映画脚本家。趣味で「アイドルの値打ち」を執筆中。
OLE:フリーライター。自他ともに認めるアイドル通。
島:音楽雑誌の編集者。
横森:写真家・カメラマン。
前回の場から引き続き。今回は雑談の部分。
「群像劇と人間喜劇」
楠木:作品(『ネーブルオレンジ』)どうのこうのではないんだけど、この映像のラストあたりで小川彩と筒井あやめが並んで踊っているシーンがあるでしょう?こういうのに魅力を感じるようになってしまってね、最近。
島:そういうのってヲタク特有の視点ですよね(笑)。
OLE:塩月希依音っているじゃない?NMB48の。彼女は2017だか2018年にデビューして、去年、2024年にセンターに立った。今19歳。素晴らしいね。小川彩もこういうキャリアを歩むんじゃないかな。
楠木:あとは……、池田瑛紗。このMVをみると、表情の作り方がうまくなったのがわかる。考えてる。
横森:見た目は渡辺麻友。中身は指原莉乃ってことなら、そりゃ売れるよ。
OLE:言葉の運動神経も感心するが、これだけ戦略的にやって成功したアイドルっていないんじゃない?
楠木:目を閉じますよね、一人だけ。これが振り付けなのかどうかはわからないけれど、もし個人の裁量であるなら、詩を解釈しているんだと思います。このMVは、少女たちが電車に揺られて、眠りこけて、到着駅でアイドルとして目覚め歌い踊る、というのが全体の流れで、要するに幻想の世界にたどり着いた少女たちのアイドルへの変身を描いている。このたどり着いた場所が幻想であるという点は、歌詞のシチュエーションと響きあっているように感じます。たとえば『神様のボート』(江國香織)のラストとすごく似ていて、主人公の「僕」が降り立った街は、現実か仮想であるのか明示されていない。なぜ仮想の可能性があるのかと言うと、過去の記憶を追いかけている点と、やはりそれを歌うのがアイドルである点が大きい。仮想というのは、要するに「奇蹟」ですね。過去の恋との遇会を求める。可能性が低ければ低いほど、それは奇蹟、言い換えれば、つまり運命になる。主人公は無垢にも運命を信じている。こうした憧憬が仮想を眼前に広げていくんです。なので、この作品で、眠る、目を閉じるというのは主題的な表現だと思います。池田瑛紗がどう詩を読んでいるのかはわかりませんが、肝要なのは、こうした感慨を、作品を観る人間にアイドルがしっかりと与えてくれている点です。
横森:イメージとしては、『なぎの葉考』に近いよ、これ。
楠木:野口冨士男と云うよりも、この場合、秋元康の作家としての立場ってポールドコックに近いと思う。メロドラマを書くうえで、凡庸な作家では諦めちゃうような表現を、しっかりと逃げずに書く。なぜ書けるのか、と考えていくと、やっぱりそこに「アイドル」があって、アイドルを語るために青春の引用があるからじゃないか。
OLE:秋元康自身の言葉によれば、アイドルよりも音楽を前に置くってスタンスだよね(笑)。
島:詩を読んで、それを自分の言葉、文章にかえたものが小説ですよね。楠木さんの言葉を借りれば、まず秋元康の詩があって、それをファンのそれぞれが自分の言葉にかえていくことでアイドルが物語化される。であれば、詩の先行性云々の主張はかなり説得力があるように感じますが。
楠木:物語化といえば、最近は新宮一成とか、脳科学とか、AIを考えるヒントになるんじゃないかと、そのあたりのジャンルの本をよく読んでいて、人間の脳というのは、基本的には、見聞きしたことの大半は記憶できないらしい。5分も経たずに8割9割は忘れてしまう。忘れられなかった部分も、時間の経過で都合の良いように改変していく。まあこの点は特段目新しいことではないんだけど、この種の自己防衛ですか、自分を守るために記憶を消し、同時に、記憶の改変もする行為を「自己肯定」と表現できるんですね。自分を肯定することが自分を救うのだということを証明している。で、この記憶の改変を「物語化」と云うんですよ。要するに、自己肯定感の強い人は、記憶をどんどん消して、また改変して、自己を物語化しているということです。僕は自己肯定の強いアイドルを高く評価していますが、たとえば生田絵梨花とか久保史緒里とか……。
横森:自己否定の強い子が、それでも生きていられるってことは、どこかで自己を肯定しているからだよね(笑)。そりゃアイドルになる子は自己肯定が強いよ。だれもかれも自己否定してるじゃない(笑)。むしろアイドルになってから、自己肯定感が強くなっちゃう子は、逆に心配。心が消えかかっている。
島:自己肯定が言葉を消す作業なら、じゃあ自己否定は、逆に、言葉をつくるのかもしれない。あまりにも短絡的ですが(笑)。
楠木:それはわからないけれど、感情の発生、つまり言語の発生を、音楽やジェスチャーに認めるなら、たとえばAIが音など言葉以外のものを駆使して、まだ言語を持たない幼児と接するとき、そこにはあたらしい言語、AIだけの言語が生まれるんじゃないかって妄想してね、インタラクションを通じて、新しいコミュニケーションシステムを創出する、とか。でもこれを実際にAIに質問してみたら、AIと人間の共進化だなんだ言いはじめて、急に安っぽいSF映画のような話題に落ち込んでしまったので、やめました。
島:今のチャットAIって「私は感情を持ちません」と言い切る割には、小説や映画の感想を得意とする。感情をもたない存在が、どうやって感想を作るのか……。
楠木:僕が面白いと思うのは、感情を持たないAIの言葉にたいして呆れたり、ムキになったり、感情を抱く人間が多いであろうという点です(笑)。
OLE:チャットAIは言葉を記号的に組み合わせて、パターンで「感情表現」を文章にしているだけではあるが、実は人間も、やっていることはそこまで変わらない。
横森:記号ってことならさ、秋元康ってさ、意味を極端に削って記号になったタームこそがじかに社会の時代をあらわすんだと固く信じているよね。「勝たん」「承認欲求」「Z世代」とかさ。
島:秋元康に文学性を見出すなら、詩人としてのスタイルは、ドゥルーズとガタリで言えば、ガタリなんだと思う。詩は、哲学から外れたところにあらわれるわけでしょう?離れたのがどちらが先なのか、僕には口出しできませんが(笑)。ガタリのスタイルって哲学から外れたことで、詩や小説を先行しているように感じます。
楠木:そういえば、絓秀実が、ガタリの新語を作り出す姿勢を言葉の記号化と表現していた。言葉を記号化することは現実への場面対応だと。秋元康が言葉の記号化、特に若者による言葉の記号化に過敏になるのは、やはり音楽の内に現在の社会=時代を常に閉じ込めようとしているからでしょう。ところで、『ネーブルオレンジ』に救われた心地になるのは、なんだかんだいっても乃木坂はアイドル群像を保っている点です。賀喜遥香、中西アルノという強い主役がいて、近傍には遠藤さくら、井上和がいる。この4人は楽曲、音楽の場面において様々な相貌を描き出せています。その後ろには池田瑛紗、小川彩、川﨑桜、それに奥田いろはだっている。1期の頃のような群像劇を印せている。アイドルグループにおける群像劇って、アイドルと音楽の関係性を考えると、やはりバルザックの人間喜劇なんだとおもいます。群像劇というものは、登場人物のそれぞれが、それぞれの物語で主役として描かれる、人物の再登場がある、これだけでは成り立ちません。群像劇の”かなめ”は、同じ人物が様々な物語、社会の様々な場面に再登場し、そこでそれまでとは異なる顔を見せる、つまり人間の多用な一面を描き出すことで社会の様相を教える点にある。つまりそれを裏打ちするのが秋元康の詩になるんだとおもいます。
2025/03/31 楠木かなえ