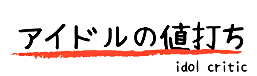日向坂46の『お願いバッハ!』を聴いた感想

「アイドルの可能性を考える 第五十七回」
メンバー
楠木:文芸批評家。映画脚本家。趣味で「アイドルの値打ち」を執筆中。
OLE:フリーライター。自他ともに認めるアイドル通。
島:音楽雑誌の編集者。
横森:写真家・カメラマン。
「『お願いバッハ!』のMVを観る」
島:前回の「僕が見たかった青空」の新作と比べると、クオリティが高く感じますね。同じアイドル作品ですが、素人目にも明確に差があるように感じる。
楠木:渡辺莉奈が生き生きして見えますね。真ん中が似合うんだ、このアイドルは。
横森:思いきったフォーメーションなんでしょ?これは。
OLE:そうだね。作り手の期待の表れだね。
横森:この子が前に出てくるとグループのイメージがガラッと変わるね。
楠木:ところで、小坂菜緒って明らかに前作でブレークスルーを起こしたと思うんだけど、どうかな。サイトに寄せられた読者からの感想を読んでいても、同じように感じている人がけっこういる。
横森:表情に深みが出てきたね。
島:現役のアイドルでは一番ですよね?
楠木:強引ですが、アイドルシーンにも小説のように「内向の世代」が出たのだとすれば、小坂菜緒はその象徴だと思う(笑)。内向を描き出せるようになったというよりは、内向的であることの価値、魅力を音楽を通して教えられるようになった、ということかな。
OLE:『Love yourself!』がそれに当たるんだね。
楠木:『Love yourself!』の印象に引っ張られた感慨だけれど、『お願いバッハ!』はMVだけ見ると、これはバッハというよりはショパンだよね。バッハを考えた歌詞に引きずられている部分と、公衆的なクラシックのイメージが対立しちゃってる。
OLE:ショパンはもう乃木坂だかで使ってる。
楠木:その手の制約を課したとすれば、やっぱり工具なんですね。「バッハ」も「おひとりさま」も秋元康のなかでは言葉の価値が同じだということです。
島:でもバッハって破滅的な明るさと暗さがありますよね。どんな作風の音楽でも希望に移し替えるショパンだとこの曲調はアイデアとして出ないですよ。
横森:だから映像と合ってないんだよね。バッハの役目を考えちゃって歌詞が音楽とまとまらない(笑)。
OLE:バッハに個別的な役目なんかないよ。だってこれは花の名前でも良いわけでしょ。ジャーマンアイリスでもネーブルオレンジでも。そこは問題にならない。
島:ジャーマンアイリスやネーブルオレンジでは引用にならないですよ。これはバッハを引用しています。
楠木:いや、ジャーマンアイリスやネーブルオレンジも引用ですよ(笑)。
島:ネーブルオレンジは比喩じゃないですか?
楠木:過去を参照しているんだから引用ですよ。バッハやネーブルオレンジをどうこうしたいわけじゃなく、バッハやネーブルオレンジが発想を支えているってことなんで。比喩は詩への解釈に過ぎない。引用をするということは、それを考えることで、自分だけの、あたらしい発想を得るということです。
横森:でもこれはバッハが主題になっちゃってるよね。「バッハ」の乱用が目立って、「バッハ」のことを考えてしまう。『ネーブルオレンジ』は、なんでネーブルオレンジなんだろう、って考えはしないけど、これは、なんでバッハなんだろう、って考えちゃうよね。そういう意味では失敗していると思う。
楠木:バッハを引用することと『G線上のアリア』を音楽をもって批評していることを整理できていないんだよ、それ。村上春樹がシューマンの『謝肉祭』への批評を小説にしたのと同じことを音楽でやっているだけだよ。『G線上のアリア』への個人的な妄想の飛躍でしょう、これは。
OLE:そもそもこれって秋元康の私情ではない気がする。私情のないところにこういった引用や批評は成立するのか。バッハがほんとうに秋元康の青春の一部分だって言うなら俺は謝るけど(笑)。
楠木:秋元康って、私情をおさえた作品のなかに強い私情を引用することがありますからね。そう考えるとやっぱりこれはバッハをウンベルト・エーコのような批評スタイルで語っているんですね。バッハを音楽の物語にしているので。バッハをペダンチックに語っていないから、まだ救いはあります。
島:以前、楠木さんが秋元康は唯一のアイドル批評家だと言っていたけれど、批評を小説的な文章にしてしまうウンベルト・エーコとかローラン・ビネ的に秋元康を見れば、たしかに、しっくりくる。
OLE:問題は、そういった批評=歌詞と音楽が最終的に作品を時代風潮に落としている点かな。
横森:なんだっけ、『ハルジオンが咲く頃』の山戸結希とか、まあやってることは同じ。
楠木:あれはファンへの追従でしょ。『お願いバッハ!』はアイドルよりもっと広い話題を見ている。
OLE:一応、こっちはダブルセンターに意味を持たせてはいるが……。
楠木:詩作において批評的に物語を作るって点では、時代に逆らっているようにも見えますけどね(笑)。「バッハ」でも「おひとりさま」でもなんでもいいからテーマを一つ決めて、それを批評する。それを音楽にするっていうのは、多作を使命にした作詞家ならではの境地だと思う。特に、若者の内面にペンを向けることがアイドルの魅力につながらないのは、批評的な転回が足を掴んでいるんだと思う。たとえば、E・サイードの云う、現代で古典的小説があるとすればそれは批評にほかならないというのは、本来の文脈としては、言葉によって世界を形作ることで世界を知っていく、という点に小説の魅力があり、今日ではその役割を果たせるのはもはや批評だけだと、予見していたわけですが、そうした文脈から外れて、もっと単純に、文体や描写ですね、たとえばスタンダールやディケンズ、ドストエフスキーなどの古い作家の文体や言葉を用いて文章をつくっているのは、この現代ではもっぱら批評家連中だけなんじゃないか。と、こうした転回ですね、こうした転回が批評をつくるわけです。もっとわかりやすく言えば、たとえば、スタンダールの『赤と黒』のなかで作家が編集者と作品のあり方について討論するシーンがある。作家は、恋愛小説のなかで政治を語る行為は、音楽会の最中にピストルを撃つようなものだから、政治など作品に取り入れるべきではないと云う。それに対して編集者は、それはあなたがこれまでに標榜してきた小説のスタイルに反すると返す。小説は社会を反映してしかるべきだというスタンダールのかつての主張と食い違っていることを指摘する。福田和也はこのシーンへの批評として、こうしたシーンを小説内に描き出すことこそが、なによりも小説の世界観を壊している、と指摘する。そしてその破壊こそがスタンダールの目的だと云う。こうした発想の転回が、批評の”かなめ”になりますが、秋元康も詩作において「転回」を用いることが多い。『おひとりさま天国』なんかは作風そのものに批評的な転回を用いています。なんたって「おひとりさま」をアイドルに歌わせることで天国にしちゃうんだから。そういう意味でも秋元康は批評家なんです。
横森:転回と言うよりも阿部和重的な偽装だよね。詩は映像ではないから、好きなだけ嘘がつけるし、世界やその設定をいつどこで変えても良い。保坂和志的に言えば、部屋に時計があることを文章に起こさなければ、読者にとってはその部屋に時計があるかどうかは想像の範疇を出ない。裏を返せば、作家はいつでも自由にその部屋の壁に時計という新事実を付け加えることができる。
島:そういう仕掛けが音楽的な興奮につながっているのかと言うと……。
横森:それはアイドルソングへの向き合い方次第ってことだから。この曲を聴いて「恋」を応援された当事者は興奮するんじゃないのかな。でもさ、単純に、バッハと若者じゃ青春の距離に時差があるよね(笑)。
島:詩の内に描かれている言葉の感覚を読むかぎりでは、これは若者の内省ですよね。でも若者の会話って、特に恋愛なんかはもっともっと短文ですよね。詩的とまではいかないけど。すごく短い。そういう部分での想像力が物足りないのかなと思います。あと、これを言ったら元も子もないかもしれませんが、若者って恋をここまで分析的に内省するものかなって、思わなくもない。右も左もわからないのが、若者の恋だと思いますよ。
横森:内省的にならざるを得ない若者の恋の部分をくり抜いているんだから、そこは問題にならないよ。
OLE:乃木坂の増田三莉音が太宰治が好きらしいけどさ、若者に受ける偉人と、そうじゃない偉人がいるんだよな。そのへんはセンスってことになるのか、それとも自分の趣向を押し通すのか。
楠木:太宰治にも明るい作品がある、って言っていましたよね。太宰治が明るい作品を書いた理由は、第二次大戦中、日本の社会が暗い雰囲気に覆われた点にあります。太宰治は自分探しという青春をテーマにした作家なので、青春というのは社会への反抗ですから、戦争によって暗くなった社会への反抗心が明るい作品を書く原動力になったわけです。だからその「明るさ」には時代を越えて若者に共感される部分が多く残っているんだと思います。
OLE:そう言われると、バッハでこれだけ練った批評の物語=音楽を書くなら、その熱量で得意のヘミングウェイを用いたほうが良かったかもね(笑)。
2025/08/30 楠木かなえ