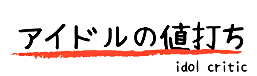「中川智尋」と書いて「逸材」と読む

「新たなアイドルの輝き」
最近は、石川九楊の『日本書史』、J・D・ボルターの『ライティング スペース』を久しぶりに手にとって、時間をかけて、ページを行ったり来たりしながら、読み進めている。文字は、絵画のように「線」によって構成された「表象」ではなく「字画」に成立する「力動の姿」つまり「痕跡」であり、書き手の精神と身体の演劇にほかならない、とか、無文字は音楽を育み、文字は書を発展させる、すなわち発音記号の傾向に強いアルファベットは音楽に強く、逆に漢字は書物の発展に寄与する、とか、『現代文学』でなぞられているとおり、目新しさはほぼないが、大人になった今読んでみてもなかなかの刺戟を『日本書史』はもたらしてくれる。ふと思いついたが、福田和也の『日本の家郷』の書き出し部分は、この『日本書史』に学んでいるのではないだろうか。
僕が最も興味を抱いたのは、石川九楊の「文字」への熱誠が、『ライティング スペース』で言うところの電子メディアの登場による書物の統一性の破壊にその芯を砕かれているように感じる点だ。『ライティング スペース』では、印刷書籍の登場によって書物に統一性がもたらされ、その統一性が電子メディアの登場によって徹底的に破壊されることを予見している。元来、たとえば中世などでは、関連性をもたないテクストの数々を一冊に綴じ合わせ、それを一つの「書」とした。時を経て、印刷技術の発展により、出版業界は市場の要請に従うかたちで、小説は小説、音楽は音楽と、書物に統一性をはかるようになった。音楽雑誌を開けば、音楽のことを考えた言葉が連なり、哲学書では哲学を、政治なら政治のことを考えた言葉に、書物はまとまる。次に、この統一性が、電子メディアつまりインターネットの誕生によって破壊されたわけだが、ここで安易にも想うのは、電子メディアの登場によって書き手もまたペンからキーボードへと決定的に移行し、文字を切り貼りするようになった今、画面に表示されるその言葉に果たして「痕跡」などあるのだろうか?という点。もちろんこの現代で手書きで原稿を書き切るなんてことは時代錯誤にもほどがあるが……、しかしまた同じ書き手であっても、手書きと、キーボードを用いる場合とでは同じ文章にはけしてならないということもまた、事実としてある。たとえば村上春樹は、自己の作品を省みて、手書き時代の作品はもう二度と書けないと、云っている。やはり、キーボードをもって文字に「痕跡」を残すには、より「精神」の動きに傾かなければならない、より文章を書くことに純粋にならなければいけない。
と、こんなことを僕は最近、考えている。文章を書きながら考えたり、音楽を聴きながら、考えている。音楽でいえば最近は乃木坂の新曲を繰り返しよく聴いている。『ネーブルオレンジ』は、あきらかにこれまでの表題作とは制作上の作風をかえて、アイドルの歌唱表現に音楽の軸を求めている。井上和と中西アルノという個性の対極したメンバーをセンターに並べたことで、個人のスタイルの際立った音楽を構成することに成功している。たとえば「THE FIRST TAKE」などが顕著だが、グループアイドルソングの独唱という構図に付随する違和感を、今作品はつくらない。詩の世界観も相まって、日常の、様々な場面で、口ずさまれるような、そんな音楽を編み上げている。けれど、ファーストテイクを聴いて僕が思ったのは、センターによる独唱よりも、複数のアイドルの個性が入り混じった、統一性を欠いた斉唱のほうが、音楽としてはまとまりがあり魅力的に感じるという矛盾だ。
ここで『ライティング スペース』に着想を得ると、ボルターはテクストの紛雑した中世の書物にたいしても一定の理解において書物の物理的なまとまり、同一の観念から出た、同一の言語関係を認めている。その理解に向け子供のように無垢に、直感的に反抗するなら、むしろ、まとまりのない、ジャンルに縛られない書物にこそ、真に統一性は宿るのではないか。寄せ集められた文字、文学テクスト、宗教学を裏書きした断片、日常生活における実用的な記録、走り書きなどが混在した、異なる領域の横断を許した書物はジャンルの固定が捉えにくいがために、読者はそれを物理的な、まとまりのあるものだと認識していくのではないか。反対に、まったく同じ色、要素を集めても、そこには単調さしか生まれない。中世の書物に真の統一性を見るのならば、印刷によってその書物たちを細かにジャンル分けする行為こそ、統一性の破壊にほかならないのだ。あるいは20世紀の小説家、とりわけフランスの作家連中がテクストの破壊に挑みつづけたのは、市場による統一性の偽りを看破していたからなのかもしれない。
統一性への誤解は、アイドルシーンにも散見する。とりわけ既存のアイドルグループにあたらしく加入する若手アイドルへの反応に顕著だろう。個性の違った、生まれも境遇も才能も異なる少女たちが一箇所に集うからこそ、そこに美しい統一性が生まれるはずなのだが、作り手、またファンの多くは、乃木坂なら乃木坂、日向坂なら日向坂、櫻坂なら櫻坂らしいアイドルを、求め、また作り上げようとする。僕が中西アルノに引かれるのは、本来の統一性を分解して作った偽りの統一性をその身をもって破壊し、乃木坂に真の統一性をもたらしているから、なのかもしれない。そもそも統一性なるものになぜ価値があるのか、疑問を抱く読者もいるはずだが、その問いに答えるならば、それはひとえに、統一性をもったものこそ継承しえるからだ、となるだろうか。
こうしたイノセンスをアイドルシーンにこじつけ、乃木坂46の6期生、日向坂46の5期生、櫻坂46の4期生を眺めれば、おのずと僕が理想とするタイプのアイドルは絞られてくる。乃木坂なら増田三莉音、日向坂なら大野愛実、櫻坂なら中川智尋。3名に共通するのは、一見してわかるとおり強い主人公感を示しながらも、それが、各グループの、既存の主役たちとは異なる輝きであるという点だ。特に中川智尋は別格に思う。櫻坂46のこれまでのどのメンバーにもない可憐さをもっているように感じる。それはたとえば、櫻坂46の前身にあたる欅坂46の傑作『二人セゾン』の世界観をもう一度グループの物語に引き出すような、希望を抱かせるほど、優れて儚い美しさだ。
2025/05/06 楠木かなえ