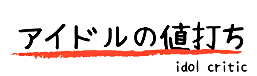僕が受けた、アイドルからの影響[文芸批評家が選ぶアニメ 10選]
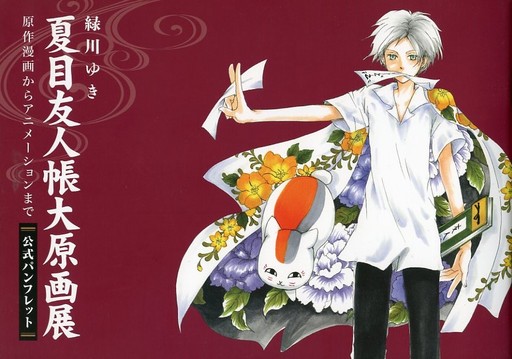
「アニメ、ドラマ、映画 10選」
「干物女」をテーマにしたテレビドラマ『ホタルノヒカリ』のなかで、とても印象深い場面がある。主人公・雨宮蛍の恋人であり同居人でもある高野誠一が蛍を自室に呼び、自分のベッドの上に脱ぎっぱなしにしてあるシャツやらネクタイやらを指し、僕はもともと几帳面な性格だけれど、君と暮らすようになって、こんなふうにいい加減になってきた。でもこれは良い影響なんだ。というようなことを言って、主人公の蛍を励ますシーンだ。
アイドルを好きになって、僕の生活は、どのように変わっただろうか。日常のどの部分に影響が出ただろうか。そんなことを最近よく考えている。まず思いつくのは、やはり音楽ということになるだろう。
僕はこれまで音楽に関しては比較的に幅広く、クラシックからジャズ、ロックからヒップホップ、そしてポップスまで、ジャンルを絞らず接してきたけれど、最近はアイドルソングが全体の2割から3割を占めているように思う。アイドルソングの魅力は、ほかの音楽とは異なるかたちで、なかなか複雑で、とても一口には言えない、独特さがある。活力だとか、幼稚さだとか、ジャンルとしての規定はともかく、まずアイドルがあって、そのアイドルの魅力を音楽の内に知ることで音楽の世界が広がるという部分が、僕にとってのアイドルソングの魅力だと言えるだろうか。これはもしかしたらアイドル本人にしてみれば不本意な、音楽への不純な接し方ではあるのかもしれないが。たとえば正源司陽子がギターを片手に歌を口ずさむだけで、僕は感傷に包まれてしまうのだ。ヴァルネラブルに澄んだ彼女の歌声に触れる度に、その楽曲の内に、以前の自分では気づけなかった魅力を知る。自己の発想力では至ることのできなかった詩的世界を前にして、音楽に囚われる。そうした経験がそのまま、過去を振り返り、過去に出会った様々な人たちのことを考え、過去の自分では表せなかった言葉をもって語りかけてしまうという無垢な行動に、より自分を走らせる。正源司陽子が歌えばどんな曲でも素敵に聞こえるのか、楽曲そのものが元々素晴らしい出来栄えであったのか、断言できないが、とにかくそうやって、僕は、アイドルソングに夢中になっていく。
もうひとつ、アイドルから受けた影響として、「アニメ」がある。
佐藤亜美菜に始まり、近年なら佐々木琴子、賀喜遥香など、アニメが好きだと話すアイドルを眺めるうちに、実際にそれがどれほどのものなのか、次第に強く好奇心を宿すようになった。
僕は、ほとんどテレビを見ないで育った。小学生の頃に、交通事故に遭って、一時的にではあるが、激しい運動ができなくなった。その頃から本を少しずつ読むようになったが、それよりも生活の中心になったのはピアノだった。祖母が元ピアニストであることも相まって、祖母に音楽における芸術のイロハを叩き込まれる、音楽的素養のある暮らし向きになった。中等部にあがると、やはり同じように交通事故に遭ったクラスメイトの女子と、毎日、放課後、ほかの同級生が部活動に励んでいるなか、ふたりで図書室に行って、本を手に取るという生活を送った(僕が通っていた学校には運動部しかなかった)。高校生になり、思春期まっただ中に立つと、ピアノではなくギターを弾くようになった。この頃にはもう僕にはピアノの才能など微塵もないことが、誰の目にも明らかになっていたので、ピアノから離れることにたいして落胆されることはなかった。僕自身、リヒテルやマルタ・アルゲリッチを初めて聴いたその時点で、天才とはどのような人間であるのか、じゅうぶんに理解したし、自分がそうした役目を天から頂戴していないことも、よくわかった。そういう意味では、ピアノの世界は健全と言えるかもしれない。夢というのは、叶えるよりも諦めるほうが遥かにむずかしいものだが、ピアノにかぎっていえば、諦めるのは容易だ。
ギターは、僕のこころを軽くしてくれた。自分の言葉にあわせて、自分のリズムで好きに歌を唄えることに、僕は夢中になった。友達といるときも、恋人と過ごすときも、ぼんやりとしているときも、どんなときもギターを弾いていた気がする。ある日、恋人が部屋に遊びに来ているとき、ちょっとした用事で友人の家に行ったまま、自分の部屋に恋人を残したまま、友人と日が暮れるまでギターを弾くという出来事があった。家に帰り、自分の部屋のドアを開けた時にようやく、恋人が遊びに来ていたことを思い出した。ギターを現実逃避の道具にしている自分の姿に気味の悪さを覚え、このままではダメだと思い、僕はしばらくギターを置くことにした。高校2年になると、将来のことを考えて外国語の翻訳を練習するようになった。これまで以上に、本を読むようになった。
このように、僕の青春時代には「アニメ」が入り込む余地は、ほとんどなかったように思う。アニメを、アイドルたちのように、若者の感情のいち部分として語ることは僕にはできない。たとえば池田瑛紗が好きなアニメに『エヴァンゲリオン』を挙げたとき、僕が考えたのは、東浩紀によるエヴァンゲリオン評で、デリダ論をもって一世を風靡した新鋭の批評家がそれとまったく同じ言葉をもってアニメ=エヴァンゲリオンを語る姿は、当時、サブカルチャーの枠組みを徹底的に壊した出来事として文壇を騒がせたという。エヴァンゲリオンが画期的であったのは、――画期的という表現は誤りかもしれないが――、文学小説のように複雑に作品を結構しているからと言うよりも、小説が本来もっていた引用と参照によって現実をあきらかにするという構造を動画に横取りし、小説の敗北を決定的にした点にあるのだという。脇目もふらず自己を言及していく庵野秀明を前に、小説を語るよりもアニメを語るほうが有意義だとする現状に、当時、たとえば福田和也は皮肉に笑っている。
と、このように、僕はアニメに対して退屈な視点しか持ち得ない人間なのだが、それでも最近は、好きなアイドルに影響されて流行りのアニメを力むことなく、楽しむようになった。とくに最近は、映画の脚本を書く合間に、アニメを楽しむことが多い。もちろん、映画やテレビドラマもよく観るが、アニメに関してはほとんど人生で触れてこなかったので、宝の山を発見したような気分だった。先日、顔見知りの女性編集者に勇気を振り絞って『ソードアート・オンライン』の話題をふってみたら、思いのほか、話が弾んだ。これを「良い影響」と言うのだろう。
と、前置きが長くなったが、今回は比較的近年に鑑賞した作品のなかで、これはと思うアニメ、テレビドラマ、映画作品をそれぞれ10本列記してみる。混同しても良いものか、迷ったが、アニメは映画作品もふくめた。
アニメ
夏目友人帳
魔女の宅急便
もののけ姫
HUNTER×HUNTER
エヴァンゲリオン
無職転生
進撃の巨人
クロスゲーム
この世界の片隅に
ソードアート・オンライン
・もっとも心を動かされたのは『夏目友人帳』になるだろうか。情感の豊かな詩的な作品で、四季折々の日差しのもと、あやかし(妖怪)との交流を通して過去と対峙し自己を発見していく主人公の成長の物語だが、その主人公の成長が、主人公との出会いを生きることの岐路にしていく他の登場人物たちの成長に支えられたものであるという点に大きな希求がある。身寄りのない主人公を引き取った藤原夫妻にかかわるエピソード群が特に素晴らしい。
ドラマ
ゲーム・オブ・スローンズ
オザークへようこそ
ホームランド
ROME[ローマ]
ウェントハース刑務所
ウォーキングデッド
ブレイキング・バッド
ストレンジャー・シングス
極悪女王
クイーンズ・ギャンビット
・完成度で言えば、後半やや尻すぼみになるが『ゲーム・オブ・スローンズ』が頭一つふたつ抜けている。個人的には『オザークへようこそ』がオススメ。暴力が人間の感情において最もソリッドであるということを予測のつかない場面展開をもってスリリングに伝える。『ブレイキング・バッド』や『ウォーキング・デッド』といった先行作品からの影響を安易な模倣に終わらせるのではなく、作品の独自の魅力に役立てることに成功している。『クイーンズ・ギャンビット』は言葉の本来の意味における「アイドル」の誕生を、作品世界だけでなく、その作品を演じた少女が現実においてスターダムにのし上がるという現象をもって叶えている。
映画
スリー・ビルボード
プリズナーズ
パーマネント野ばら
ザ・ブックオブヘンリー
ベイビーわるきゅーれ
志乃ちゃんは自分の名前が言えない
雨の日は会えない、晴れた日は君を想う
ミスミソウ
偽りなき者
恋は雨上がりのように
・『スリー・ビルボード』に、強い衝撃を受けた。人間の本性として現れる衝動的な暴力こそが事態を好転させるのだという希望のあり方は、日本人がそなえ持つ感情ではとても太刀打ちできないものだろう。その点では『オザークへようこそ』と類似している点が多々あるが、こちらはよりシンプルに、シリアスを捨てた暴力だ。一方で、『ベイビーわるきゅーれ』は日本人だけが持ち得る無関心な日常と、その日常の隣にひそむ非日常への期待を、やはり日本人特有のコミカルな一面をもって表現している。日本の映画にもまだまだ可能性があることを教えてくれる。
2025/08/27 楠木かなえ