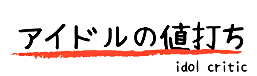乃木坂46の『ビリヤニ』を聴いた感想

「ビリヤニって何?」
「才能以上のものを書くことはできない」これは日本文学のメインストリートで50年以上にわたって小説を書きつづけた正宗白鳥が死を迎えた際に、最後に言い残した言葉だ。天才だけが達する境地というものがある。日本の文芸批評の創始者である小林秀雄は正宗白鳥の言葉を聞いて、愕然としたらしい。
戦後の日本文学10選に入るであろう『抱擁家族』を書いた小島信夫は、ある時期から、小説を一筆書きでつくるようになったという。一筆書きというのは要するに、原稿用紙に一度ペンを落としたら、それを書き直すことはない、ということだ――だからというわけではないはずだが、小島信夫の作品には、たとえば順接の「が」に無頓着な箇所を発見することがある。天才だけが達する境地というものが、やはりある。ところで、やはり天才である詩人・谷川俊太郎は、むしろ老境に入ってから詩を頻繁に書き直すようになったという。境地と言っても、人それぞれ。
僕はまだまだ若輩者だし、そもそも「天才」とはほど遠い凡人ではあるのだけれど、それでも8年、アイドルを眺め、文章を書きつづけてきたことで開きつつある境地がある。
アイドルの本領・使命は「活力」だと思う。もちろんこれはアイドルファンならば誰でも抱く感慨ではあるが、考え、そこに至った、という点に意味がある、と思う。また、ここで言う「活力」は「救い」ではない。なにものかに救いを求めるということ自体、どうしようもなく救われない行為であるから、アイドルに救いを求めることは、活力を得ることと同意にならない。ここで言う活力とは、とりわけて言えば、ファンの心に平穏をもたらす、心の励ましにある。それはどのような励ましだろうか。それはおそらく、そこに在る、つまりそこに存在する、ということにもたらされる励ましではないか。日常生活の場面に例えて言えば、朝、目が覚めて、今日一日のことを考えると、今日中に終わらせなければならない仕事のことを考えると、とても憂鬱になる。働いて生きていく以上、こうした憂鬱から逃げることは誰にもできないし、家族、友人、恋人のいずれも、この憂鬱に介入することはできない。なぜなら、かれら彼女らは時に感情をじかにあらわにする存在、過酷な現実をつきつける存在だからだ。アイドルは違う。アイドルは、たとえば『孤独のグルメ』の主人公のような、刺激を意図的に抑えた、批判精神を極限まで削った、感情のぼーっとしたイノセンスをもっていて、誰かを傷つけることをしない。『孤独のグルメ』の主人公にとって食べることが最高の癒やしであるように、アイドルもまたファンにとってそのような存在なのだろう。アイドルは、朝の冷気を払い、布団から這い出る勇気を与える存在なのだ。
そう考えると、アイドルのことを真剣に考える、深く考える、つまり批評するという行為は、アイドルの本来の魅力からどんどん遠ざかる行為だと断言できる。アイドルの魅力を考え言葉にする行為が、アイドルの魅力からもっとも距離をつくる行為だという事実は、僕を間抜け者として映し出す。つきつめてしまえば、アイドルというのは、口に出して語ってはならない存在なのだ。空間だけにただよう、神聖な存在なのだ。
そう考えると『ビリヤニ』はすごく良い。これがタイトルが『めだまやき』だったら、あまり良くない。なぜって、目玉焼きにはそれぞれその人なりの食スタイルがあるはずだから、批評精神が宿ってしまう。『ビリヤニ』には、たぶん、そういった意識は、すくなくとも日本人には、ないはずだ。だから『ビリヤニ』にたいしてはこれ以上考える必要はないし、それがどんな料理なのか、どういう味がするのか、とか、知らないままでいい。『ビリヤニ』はそんな曲だと思う。詞や音楽が言葉の連なりに成り立つ以上、そこにはかならず意味が込められているはずだが、それを考えさせないところが、この楽曲の素晴らしい点だ。
ミュージックビデオも雰囲気がバッチリだ。香辛料・スパイスを魔法の粉に仕立てるのは、とてもファンタジーで、アイドルの世界観をぐっと深めている。前作では笑顔の抑制を描いた賀喜遥香も今作ではとびきりの笑顔を見せてくれているし、センターに抜擢された6期生、特に矢田萌華は華やかにミステリアスで、まだまだ自分の魅力がどこにあるのかわからないであろう少女の未知な部分が美しさとなって楽曲の魅力と一致されている。
2025年の乃木坂46の表題3作品は、優劣をつけがたい。『ネーブルオレンジ』は中西アルノの個性を活かしきったし、『Same numbers』はこれぞ真打ち登場という風格を賀喜遥香がみせつけた。
さて、これらにどう順位をつけて、アイドルソングランキングとすべきか。あ、また考えてしまった。
2025/11/10 楠木かなえ