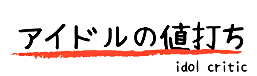乃木坂46の『Same numbers』を聴いた感想

「なぜアイドルはファンに笑顔を向けるのか」
絶望的なのは、人が鳥や草のように、ただ生きることが出来ないことではなく、素人の小説や下手なピアノにやりきれなくなってしまうということだ。そしてそこに輝きの片鱗を見い出せなくなることだ。
福田和也/「アントン・チェホフ」
「『無能だというのは』と、スタルツェフは思った。『小説を書けない人のことではなく、書いてもそのことを隠せない人のことだ』」*1。小説を書き、またそれを世間に向け公開せずにはいられないその精神を「無能」だと言うこのスタルツェフの独白に福田和也は作家の立場から同意しつつ、しかしまたこのスタルツェフの独白、あらゆる「無能」を遠ざける人生こそ人間の最も悲惨な一面であると言い切っている。過去に恋した女性との再会に際し、平凡な大人へと成長したその女を眺めながら、あのとき結婚しないで良かったとつくづく思う、そのスタルツェフの横顔ほど悲惨なものはない、と。この福田和也の視点を鍛えたのは、おそらくは高浜虚子の文学に違いない。
高浜虚子といえば、近代文学史に銘記される俳人であるとともに夏目漱石を文学的アイドルに育て上げた人物として知られるが、一方で――特にこれは福田和也が結晶した虚子の像でもあるが――虚子は、チェホフに描き出されたスタルツェフのような、一見すると高い文学的志向をもった人間にたいして激しい葛藤をもっている。虚子は、人生の絶望を文章において穿とうとする文学の傾向に浅ましさを覚え、嫌悪した。たとえば人間の絶望を描き出すにしても、真に絶望している人間にその苦境を語る余裕などあり得るはずもないと斬り捨てる。つまりそうした文章は文学を気取った知識層の遊戯、文章のソフィスティケートでしかないと虚子は看破する。
では文学とはなにか。虚子によれば、文学の役目は、たとえば死刑囚でさえも感じることのできる希望、人が死ぬ瞬間に見るであろう一点の光を描き出し、読者に勇気を与えることにある。これは、人生の悲惨さを小説に起こそうとする当時の、いや、現代においても、と云うべきだろうか、多くの純文学作家の姿勢と真っ向から対立するものだ。純文学作家からすれば、虚子の言い分は、現実から離れた、空想にすぎない。
お前は若くて、健康で、器量よしで、生きる望みに燃えている。だのに、わたしは老いぼれで、まずもって死人も同然だ。今さら、どうしようもないんじゃないか?そのへんのことが、わからんわたしだとでも言うのかね?
チェホフ/ワーニャ伯父さん(訳 神西清)
いずれにせよ今日の社会において「光」を描く者とは、だれか。すくなくとも小説にはそうした力はもう残っていないし、そうした志をもった小説家もいない。それができるのか、という問いには正面から答えることは僕にはできないが、そうした志をもった存在を探り当てることならできる。それは、やはりアイドルになるんじゃないか。すくなくとも秋元康はその種の希望と光を、ほとんど綺麗事にしか見えない音楽を、編み続けている。またそれを演じるアイドルたちの多くも、一点の光を描き出そうとする、志を確かに抱いている。
乃木坂の新曲である『Same numbers』もまた希望を歌った楽曲だ。作風そのものは、これまでの乃木坂の表題作の多くに用いられたテーマを踏襲したものとなっている。たとえば今回センターを務める4期生の賀喜遥香が初めてシングル表題作に姿を現した『夜明けまで強がらなくてもいい』とほとんど同じメッセージを発していると云って良いだろう。今作では、ある決められた一定の状況を偶然にも目撃したその出来事を日常を破る特別な光景だと捉えようとする、イノセントな人間感情を希望へと歌い上げている。「一定の状況」は、毎日どこかで、自分の身近な場所で起きているものではあるけれど、その状況は、意図して目撃するものでもない。デジタル時計の数字が揃う瞬間をふと目撃することと、大晦日のカウントダウンを待ち構える行為とでは、意味が異なる。こうした溝(みぞ)を、日常と非日常の境目を意識することに運命や奇跡、希望へのアプローチがあるのだということを、歌っている。
ミュージックビデオもまた、現実・現在と、未来――あるいはそこには過去も含まれるかもしれないが、日常と、その隣りに潜むなにかとの間隙にアイドルを立たせようとしているようにうかがえる。
考えてみれば、僕はこれまでに、なぜアイドルの無垢な部分、幼稚な部分に引かれるのか、という点をアイドルと批評を結ぶものとして考えてきたけれど、その「批評」が溝に落ちているものなのだとすれば、その向こう岸にあるのは、なぜアイドルは無垢であり、幼稚であるのかという問いなのではないだろうか。転じてこの問いかけは、なぜアイドルはファンに笑顔を向けるのか、という問いへと帰結しているかに思う。
やっぱり小林さんは、文芸批評を一本立ちさせようとして苦労した時、どうして読ませるかということを、大変に深く考えたんじゃないかと思うんです。どういう言葉で書くかということを。
それは、人を惹きつける言葉というか、文芸の世界だけに跼蹐してしまうような言葉でない言葉と、文学の世界でしか通用しないような言葉との配合をどうするかという、その配合の問題でもあり、それから、どんな呼吸で語り口を展開していったら人は随いてくるか、人はどうして驚くか、という問題でもある。
江藤淳/文芸批評家という「稼業」
と、ここまで書いてみて僕が思うのは、これはほとんど毎回そうなのだが、アイドル作品を真面目に語ることの、バランス感覚のむずかしさだ。先の引用は、小林秀雄の不在について語られた一場面で、僕はこれをアイドルが笑顔を編み上げる過程に結びつけようとしたのだが、この江藤淳の言葉は、僕自身に強く照り返す。アイドルを真剣に語ることの可笑しさをいつまでたっても拭えないのはなぜだろうか。文芸批評家は文学を芯に沈め文芸の枠を抜け出て行動する人間のことを指すが、しかし「アイドル」のハードルは変わらずに高い。アイドルを語ることは、カタツムリを踏み潰してしまったときの感触によく似ている。パリンという心地よさ、驚きのあとに、居心地の悪さ、後味の悪さを覚える。しかし『Same numbers』を聴いて、その溝(みぞ)を考えることは、僕にある種、勇気を与える。それが無垢だったり幼稚だったりすればするほど、それに向ける自分の言葉が可笑しければおかしいほど、それらが綺麗事であればあるほど、アイドルの笑顔を希求すればするほど、それはまさしく「希望」だからだ。
2025/07/07 楠木かなえ
*1チェホフ/イオーヌイチ(訳 小笠原豊樹)