日向坂46の『クリフハンガー』を聴いた感想
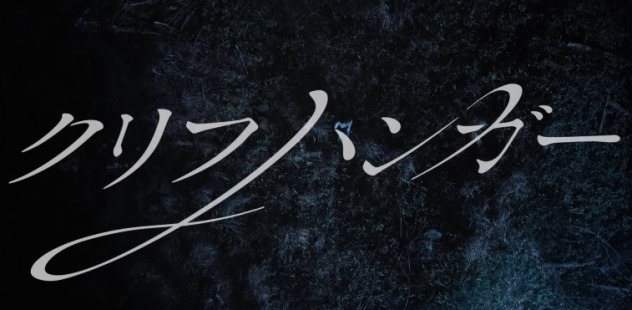
「成長する前の姿、成長したあとの姿、その間隙に輝き現れる像」
期待の新人である大野愛実をセンターに迎えた新作『クリフハンガー』がついに公開された。
作品全体をとおして、事前の期待感を上回る音楽を実現している。大野愛実のパフォーマンスは新人らしからぬものだし、小坂菜緒もまたこれまでのどの作品とも異なる表情を描き出し、ここにきてさらなる前進を見せている。その横には正源司陽子がいて、その後ろには藤嶌果歩、松尾桜がいる。最奥には渡辺莉奈が見える。ミュージックビデオを眺めながら、まず私の目を引いたのは、衣装の色づかいの素晴らしさだったが、それは複雑に、しかし一目瞭然に並び立った少女たちの魅力に受けたものなのかもしれない。
日向坂46(けやき坂46)が、音楽作品を通じてアイドルと色の関係を深めてきたグループだということは、多くのファンが見解を一致するところだろう。アイドル自身もまた、小坂菜緒から高井俐香まで、色彩に、アイドルを演じるうえでなにがしかの意味合いを得ていることを、直接言葉にしてファンに伝えている。
『イマニミテイロ』はもとより、『JOYFUL LOVE』のミュージックビデオにおいて描き出された、色とりどりの衣装を身に着けたアイドルを輪につなげた、擬似的な色相環が顕著だが、他のアイドルグループと比べても日向坂はとりわけ「色彩」にアイドルの美しさの表現を求めてきたグループだという印象を強めている。『クリフハンガー』からは、その色相環のひとつの関係としてあらわれる「補色」の存在をつよく意識させられる。
補色というのは要するに、たとえば白地と赤地を並べ、その赤地の方をしばらく眺めていると白地と赤地の境界に緑色が輝き立ってくる現象のことを云うのだが、この補色の魅力は、色相環において隣り合っている色が出現するのではなく、真向かいに位置した色が出現するという点だ。赤地と白地の境界線、つまり白地の枠線部分=赤の隣りに緑色が出現するのに、色の環を描く際には赤と緑は隣り合っていないという点が、なんとも幻想的に感じる。補色は、定義上は色相環の真向かいにある最も遠い関係だが、人間の視覚を通して知覚されるときは、その強い対比効果によって、時間的または空間的に「隣」という形で現れてくる、という二面性を持っている。
『アイドルの値打ち』の熱心な読者であれば、「幻想」「二面性」というワードを並べ始めた時点で、それらをアイドルに紐付けようとする私の思惑を察知したはずだが、これだけではありふれた情報にすぎないので、もうすこしだけ、音楽に踏み込むためのまえがきを続けようと思う。
作曲家のオリヴィエ・メシアンはこの「補色」を音楽における自然共鳴音にむすびつけている。
たとえば和音は、「実際に奏でられた音の重なり」と乱暴に解釈できるが、その和音が生み出される前に、自然共鳴音というものがある。自然共鳴音をやはり端的に説明すると、ある音を鳴らしたときにその音に別の音が内在していること、またそれを聴き分けることを自然共鳴音と言う。自然共鳴音は、基音と倍音、ひとつの音に内在する音、つまり同時的な音だが、人間がそれを感知するには、瞬間的な時間を必要とする。この、ひとつの音にほかの音が内在する点、またその音は同時的に発生しているけれど、それを感知するには時間を要するという点において、自然共鳴音は補色と類似した存在・現象だとみなせるというのが、メシアンの発想になる。メシアンいわく、ピアニストは、たとえばドビュッシーやモーツァルトは自身と同じく音に色彩を見ていたはずだと語る。
実を言うと、これは保坂和志が小説における第三の領域を考え語った文章の反復、再利用でしかないのだが、メシアンの発想を現実とフィクションという関係に求めていった保坂和志をよそに――保坂和志は、メシアンが音に色彩を見ることと、小説を読む際に頭に風景が浮かぶことを引き合わせることで小説の可能性を考えている――私はそれを、アイドルとそれを演じる少女という関係に求めていくことにする。
補色や自然共鳴音をアイドルに引用して言葉に表わすことは、むずかしくない。アイドルというのは、ある少女の、成長する前の姿、成長したあとの姿、その間隙に輝き現れる像のことを言うからだ。
その「像」のことを、一般的には、幻想と表現できるかもしれない。さらに、日常生活において私たちがもっとも幻想に立ち会う瞬間を挙げるとすれば、それはまず間違いなく恋愛になるだろう。その意味では、『クリフハンガー』が現実と理想のあいだに立った恋愛ソングであることは、あらがえない、帰結的な印象を受けるし、クリフハンガーという言葉の意味それ自体が、色彩に価値を見出すグループの姿勢と合致している。
恋愛は、現実に直面させられる、容赦のないものだけれど、裏を返せば、それはほとんどの人にとって恋愛観が幻想的なものに確立されていることのあかしと云えるだろう。まず幻想があって、次に現実を思い知らされるのが、恋愛だ。でも、あるいは、ひつだけ、たった一つだけ、現実を思い知らされない恋愛があるかもしれない。それは初恋のことだ。というか、初恋そのものが、そのひとの恋愛観つまり幻想である場合がほとんどではないか。『クリフハンガー』の歌詞と、それを歌う大野愛実という関係から想起するのは、やはり『ジャーマンアイリス』ということになってしまうが、『クリフハンガー』における主人公の葛藤は、『ジャーマンアイリス』における初恋への追憶にあると読むべきだろう。『ジャーマンアイリス』で確立された「愛」つまり「幻想」のなかでもだえる、その状態がそのまま『クリフハンガー』という予感的なタイトルに表されている。
初恋が手強いのは、幻想になった彼女は永遠にうつくしく、反論の余地がないからで、私はこうした幻想を歌った『ジャーマンアイリス』を未来も希望もないかわりに、アイドルを幻想的に、絶対的な存在に押し上げた作品だと評価したが――有彩色ではない「白」には補色がないが、しかし白を最終的な到達点として語ることはできる。白=純潔と聞くと、そこに色をつけたくなるのが人間の性だが、むしろアイドルは白になろうとする意識に成り立つのではないか――、今作『クリフハンガー』では、ただ安易に希望を付け足すのではなく、ハッピーエンドとバッドエンドの両方を予感させることで一方に確かな希望を作り出した点は、秋元康ならではといった発想に感じる。
2026/01/09 楠木かなえ



